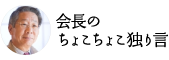実家の直ぐそばの畑を我が社のお客様が土地を購入して住まいを建てるようになった、最初はまさかと思っていたが現実になり、まもなく引き渡しのところまで来た。
このすまいより見積もりや段取りを社長に交代したばかりで、ほとんど現場には携わることはなかった、斜め前現場故に毎日進捗状態を見ていた、12月26日寒い日にふと温度計を外で見ると『外気温が9時2分時で0.8度/湿度53%』そのまま建築中(外部戸締り出来る状態)の床下に温度計を置くと16分後には『温度12度/湿度65%になった』ひゃ~すごく温い!、勿論現場であるから熱源はない、基礎断熱をしているから地熱だけの熱源が生かされている、すぐに我が家の居間で計る、暖房していて『9時25分時で温度が10.3度/湿度56%・続き間で9時49分時で6.8度/湿度57%因みに翌日6時35分時で4.1度/湿度56%』オ~寒い! 32年前に断熱材も入れてあるし通気構法の住まいにしている、途中から内窓を何ヵ所かいれてある、ただ基礎は基礎断熱でなく当時はどこも基礎換気をして根太の間に断熱施工をしている状態、今のようなウレタン断熱がなくウール系100ミリを使用していたけど・・・。今の住まいは窓(3層+アルゴンガス)・天井・壁(外断熱)だけでなく地熱の取入れ(基礎断熱)もしている。
こうしてみれば今の我が社の性能がピカ一良いのが解る、出来る事なら我が社の住まいに住みたいものですが、当時苦しい中で精魂込めて造った住まい、やっとローンが終わったばかり、まだ壊すのはもったいないと思うが、『娘は建て替えてすみた~い』といつも言っている、聞こえないふりをしているが・・・。